【#04】「年始に考える:ポピュリズムと向き合うためにできること」映画『パール・ハーバー』
Posted on 1月 10, 2017
「うっとり」から「しっかり」に
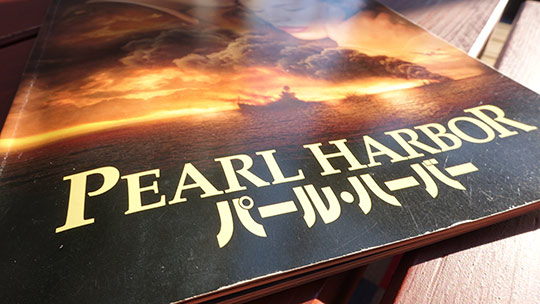
史実の紹介が長くなりましたが、こうした史実をふまえて作られた映画『パール・ハーバー』を見ていきましょう。
この映画が公開された2001年夏、日本でも大ヒットしました。当時はまだこども学部は創設されていなくて、浦和大学短期大学部英語コミュニケーション科の教員だった私は、後期科目「アメリカ事情」という科目で、12月7日直前講義で真珠湾攻撃をテーマとした講義を重ねていました。
劇場公開された数ヶ月後で、映像を使うことはできませんでしたが、受講生の多くが『パール・ハーバー』を劇場で観たことを、目をハート型にして語っていました。女子大生たちのうっとりした目が忘れられません。当時の大学生にとっては、この映画は恋愛映画に留まっていたのです。ただ、講義を聞き終わり史実を知った彼女たちの目は、「うっとり」から「しっかり」に変わり、史実を見つめなければならないことを自覚して教室を後にしていました。
この映画公開以前には、映画『トラ・トラ・トラ』の場面を私が口頭で話して、「日本軍の爆撃機が攻撃され、片翼を失ったらどうするか?」と問いかけて、受講生の反応を見ていました。今はもうこのような話をする時間の余裕がないほどに、学生たちが史実を知らないので、歴史事実の説明に講義時間の大半を使うようになってしまいました。
映画『パール・ハーバー』は、史実だけでは多くの観客の興味を引きつけられないので、恋愛映画というフィクションを盛り込んで、主人公の男女たちの友情や愛情を話の軸としています。
日本人として見る場合、問題を多く含んでいる映画ではあります。真珠湾攻撃のために空母から飛び立つ爆撃機の様子、攻撃前の機上の様子で、講義では必ず一時停止して「こんなことを日本兵は決してしない、ハリウッド映画的な解釈」と説明するのが、戦艦オクラホマ号(オクラホマも海のない州)攻撃を命じられた爆撃機の操縦桿のそばには、戦艦オクラホマ号の写真と並んで若い女性の写真が貼り付けられているのです。たとえ妻、婚約者だったとしても、当時の日本男児がすることはない、と私は思います。恋愛の要素がないと観客の興味をそそらないとの判断かもしれません。