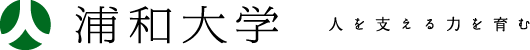福祉業界お役立ちコラム
社会福祉士国家試験の難易度

社会福祉士の国家試験は「社会福祉士及び介護福祉士法」に定められた規定により、毎年1月下旬、全国24カ所を会場に実施されます(平成28年3月現在)。社会福祉のエキスパートとして人気のある資格ですが、国家試験の出題範囲が広い上に、法令が次々と改訂されるため、やや難易度の高い試験だと言われています。ここでは、社会福祉士国家試験の試験内容と難易度などについて紹介します。
社会福祉士国家試験の試験内容
社会福祉士国家試験は、5肢択一を基本とするマークシート方式で行われます。試験時間は、午前中2時間15分、午後1時間45分となっており、合計150問の試験問題は、以下の18科目から構成されています。
なお、科目別の出題基準及び合格基準については、国家試験の実施団体である「公益財団法人 社会福祉振興・試験センター」のウェブサイトから入手することができます。
- 人体の構造と機能及び疾病(基礎医学など)
- 心理学理論と心理的支援(人の心理学的理解など)
- 社会理論と社会システム(現代社会の理解など)
- 現代社会と福祉(現代社会の福祉制度や政策について)
- 地域福祉の理論と方法(地域福祉の基本的考え方など)
- 福祉行財政と福祉計画(福祉行財政の動向、福祉計画の主体と方法など)
- 社会保障(年金、介護保険制度をはじめとした社会保障制度の概要など)
- 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
(障害者や高齢者支援に関わる法制度など)
- 低所得者に対する支援と生活保護制度(生活保護、ホームレス対策など)
- 保健医療サービス(医療保険制度の概要、診療報酬制度など)
- 権利擁護と成年後見制度(憲法、民法、行政法の概要と実際など)
- 社会調査の基礎(社会調査や統計に関する手法、活用方法など)
- 相談援助の基盤と専門職(社会福祉士の役割と意義など)
- 相談援助の理論と方法(相談援助の過程と個人情報の扱いなど)
- 福祉サービスの組織と経営(福祉サービス提供組織の経営方法など)
- 高齢者に対する支援と介護保険制度(介護予防、ケアなど)
- 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
(児童や家庭をとりまく諸問題と社会福祉士の関わりについて)
- 就労支援サービス(雇用動向や政策、就労支援の実際など)、更生保護制度(更正保護制度、医療観察制度と社会福祉士の関わりなど)
社会福祉士国家試験の難易度と合格率
医師、看護師、保健師などの国家試験は、合格率が約80~90%、精神保健福祉士の国家試験は合格率が60%前後であるのに対し、社会福祉士国家試験の合格率は、例年20~30%を推移しています(ただし、福祉系の大学別に合格率を見た場合、90%前後の合格率を誇る大学もあります)。
合格率から見ると、社会福祉士国家試験は比較的難易度が高い試験であることが分かります。出題範囲が広いことが、合格率に影響していることも考えられるでしょう。
実際に合格した人の中には、「基本的な問題が多く出題される」、「問題文をよく読むことが大切」、「制限時間内に全問回答するためには、スピードが重要」といった声も聞かれるので、しっかりと基礎を固めた上で、不得意科目をできるだけ解消し、万全を期して対策する必要があるでしょう。
社会福祉士の国家試験は、幅広い分野からの出題となるのが特徴です。法令の改正があれば、過去の試験問題だけでは対策が不十分となる場合があるので、常に最新の情報をチェックしながら学習を進めるようにしましょう。